「株式会社24Frameの内情暴露日誌」第26回:創作物病理診断チャート
 |
今回は,映像制作についてより包括的な考え方を述べたいと思います。包括とは何か? この場合分類・分析とします。分類と分析のためにはカウンセリングが必要です。仮にあなたが何かを作ろうとしているとした場合,以下の質問から始めてみましょう。
「それは実写ですか?CGですか?」
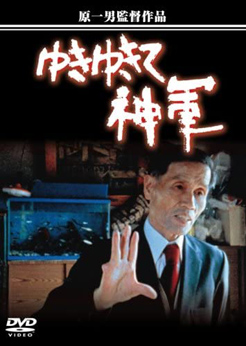 |
寺山修司じゃありませんが,今すぐパソコンを閉じて街に出ましょう。実写のよさというのは「ありものの良さを記録する」ことがその第一義。あり物の良さがよく分からなければ原一男監督の「ゆきゆきて,神軍」を見てください。良かれ悪しかれその意味が理解できるでしょう。ドキュメンタリーじゃなくて劇映画だった場合は下記の<CG映画だった場合>とほぼ同じなのでそちらの項を参照。
<CGだった場合>
次の問いにお答えください。
「それはCG映画ですか?ゲーム内映像ですか?」
 |
まず脚本について考えてください。映画の場合,脚本に書いてあることを忌憚なくつづるのが絵の役目で,場合によってはそれがCGだというだけの話。脚本があればコンテニュイティ(連続性の意。コンテとも呼ばれる)について思案することが可能になります。脚本時点で連続性が損なわれていることもあります(キャラの行動が唐突すぎて何を考えているのか分からなくなるなど)。その場合は脚本からやり直したほうがいいですが,まあ状況次第でしょうし,できる範囲で。脚本がよくない限りは劇映画が面白くなることはないので,それならすべてを無視して即興ベースでやったほうがまだいいかもしれません。とはいえその手の最高の成功例は「イージー・ライダー」とかになりますので,なんにせよ何かのハードルは高いです。
<ゲーム内映像だった場合>
この場合は脚本全体ではなく,そのシーンごとに果たすべき要件ってものがあるはずです。そんなことをいちいち考えずにゲーム全体が作られている場合も多々ありますが,まあ自分の担当か所の状況を精査すれば,ここでは何をすべき,ってのが(ある程度慣れれば)自然と見えてきます。映画と違ってゲームは長尺ですから,全体の連続性というより「このシーンが終わったらどういう感情でユーザーが何をすべきか伝える」というのがここでの本質です。(敵役が現れたら,悪いやつだよ,と改めて教え(子供を人質に取るとかでいいです),そいつを倒すためにはどうする?(頭上のバケツにズームアップのカットで締める,とか)で終了させる。
僕の例がそうであるように往々にしてここのアイデアは陳腐化しますが,それでいいです。ゲームとは本来記号からの想像で遊ぶものであり,記号というのは分かりやすさが最優先。「敵側にも悲しい過去があって,それは実は子どもにまつわるものであり,バケツでお手伝いをしてくれていたのどかな過去もある」みたいな設定をして何かが深まる錯覚に興じるのもいいですが,ユーザーにはたぶん伝わりません。どれだけCGが進化しようが「強面,人質,卑怯,悪」くらいまでが,映像情報で人に与えることができるすべての限界です。
 |
上記のような分類はあれど,基本的にユーザー/観客の集中力を途切れさせない,というのがこれらの創作物の役割ですね。それが連続性ってやつで,これを維持するにはもう一つ重要なファクターがあります。それは音楽です。
人間の脳は生存に役立つ情報に重きを置いて発達しています。意外に思うかもしれませんが「怪しい人影」という視覚情報より「謎の物音」というものに人間はより敏感に反応します。言語が発達したのも鳴き声での危機管理をベースにした「音」優先の文化で行ったほうが生存率が高い,といった感じで,
すべての価値観はいまだに(時にありもしない)生存競争の名残で決定されています。目が大きいのを美と感じるのも根本的には「視野が広そう」みたいな理由で,原始人じゃないんだから,と思いそうですが,まあ今の言語ベースの文化なんて進化に影響与えるほどの年月続いてないともいえる訳で。
 |
 |
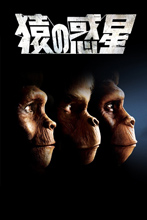 |
結局創作物の分類というのは,脳の構造と不可分で,いかに大脳新皮質から辺縁系,ひいては基底核に刺さるものを作っていくか? というのが創作物の命題です。分かりやすくいうとドットでも「異性」という記号を認識することはできますが,これは非常にロジカルな新皮質ベースの刺激。美しいものが映った写真,というのは視床下部からダイレクトに基底核って感じなので太刀打ちできない。
視覚野,聴覚野,それがどれだけ旧脳の奥に鎮座しているかという問題に加え,それが生存に関わる問題か否かなど,いくつかのルールで配線が行われて物事が決定されていく。そんなパズルを解きながら,物を作っていくのが道なれど,結局は自分が「これ!」と思うところに狂気じみたこだわりを見せれば,意外と多くの人が似たようなことを感じてくれる……というのもこれまた事実。
どこへ行こうか。ネットは広大だわ,と独り言ちりながら本日はここまでです。それでは皆さん,また次回。
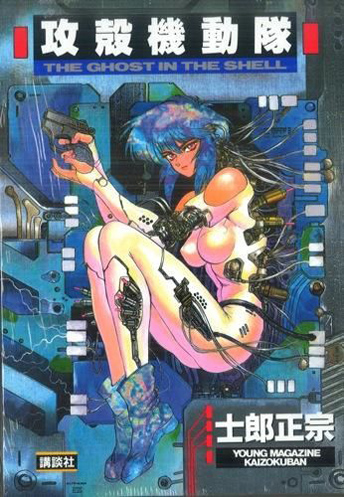 |
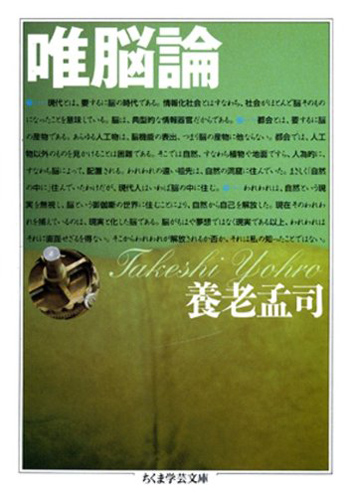 |
